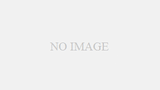67歳で、病気療養のため、一人暮らしの東京から姉の住む見ず知らずの地方都市新潟市秋葉区に引っ越してきました。この町の高齢者が、ここで、自分らしく安心して暮らすために必要な条件を考えました
参照ページ
①新潟市地域包括ケア計画
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/seisaku/keikaku/fukushi/koreisha/keikaku2024.html
②新潟市地域包括ケア計画概要版
https://www.city.niigata.lg.jp/shisei/seisaku/seisaku/keikaku/fukushi/koreisha/keikaku2024.files/gaiyouban.pdf
1. 地域包括ケアシステム
地域包括ケアシステムとは?
地域包括ケアシステムとは、高齢者が住み慣れた地域で、自分らしく安心して暮らせるように、医療、介護、予防、住まい、生活支援などが一体的に提供される仕組みのことです。
従来の医療・介護の課題
- 病院や施設への入院・入所が中心
- 地域での生活支援が不十分
- 孤立化や孤独死のリスクが高まる
地域包括ケアシステムの目指すもの
- 住み慣れた地域での暮らしの継続
- 医療・介護の切れ目のない連携
- 地域住民の参画と協力
- 予防重視の取り組み
地域包括ケアシステムの具体的な取り組み
- 地域包括支援センターの設置: 各地域に設置され、介護に関する相談や、ケアプランの作成、サービスの紹介などを行っています。
- 在宅医療・介護の充実: 病院と連携し、自宅で安心して療養できるような体制を整えています。
- 介護予防サービスの拡充: 体操やレクリエーションなど、介護が必要になる前の予防的な取り組みを強化しています。
- 地域住民の参画: ボランティア活動や地域活動を通じて、地域住民が互いに支え合う仕組みづくりを進めています。
- 住まいの多様化: 高齢者向けの住宅や、在宅サービスと連携した住宅の整備を進めています。
2.新潟市地域包括ケア計画
新潟市地域包括ケア計画とは?
新潟市地域包括ケア計画は、高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らせるように、様々なサービスや支援を総合的に提供するための計画です。
主な目的
- 高齢者の尊厳と自立を支援: 高齢者が、自分らしく生活できるように、身体機能の維持や社会参加を支援します。
- 介護が必要になった場合でも、住み慣れた地域で安心して暮らせるようにする: 在宅での生活を支援するため、訪問介護やデイサービスなどのサービスを充実させます。
- 地域住民が一体となって、高齢者を支える仕組みづくり: 地域住民やボランティアが、高齢者の生活を支える活動に参加できるよう、様々な取り組みを推進します。
計画の内容
この計画では、以下の点が具体的に示されています。
- 高齢者の現状と課題: 新潟市における高齢者の現状や、抱えている課題を分析します。
- 目標: 将来的に実現したい社会の姿を明確にします。
- 施策: 目標達成のために、どのような施策を実施するかを具体的に示します。
- 評価: 施策の効果を評価し、計画を改善するための仕組みを構築します
新潟市地域包括ケア計画の特徴
新潟市地域包括ケア計画は、他の自治体の計画と比較して、以下の点が特徴として挙げられます。
- 地域住民の参加: 地域住民が計画策定段階から積極的に参加し、意見を反映させています。
- 多様な主体との連携: 医療機関、介護事業所、福祉施設、ボランティア団体など、様々な主体と連携して、包括的なサービスを提供しています。
- 予防重視: 高齢者の要介護状態の進行を予防するため、健康づくりや介護予防の取り組みを強化しています。
新潟市地域包括ケア計画の具体的な取り組み例
- 地域包括支援センターの設置: 高齢者やその家族からの相談に応じ、必要なサービスにつなぐ窓口を設置しています。
- 訪問看護・介護の充実: 在宅で生活する高齢者に対して、訪問看護や訪問介護などのサービスを提供しています。
- デイサービスの多様化: さまざまなニーズに対応するため、通所型のデイサービスだけでなく、ショートステイやデイケアセンターなど、多様なサービスを提供しています。
- 認知症ケアの推進: 認知症の高齢者とその家族に対して、専門的な支援を提供しています。
- 地域住民向けの健康づくり講座の開催: 高齢者の健康維持を支援するため、体操教室や栄養相談などの講座を開催しています。
まとめ
新潟市地域包括ケア計画は、高齢者が住み慣れた地域で、いつまでも安心して暮らせるように、様々なサービスや支援を総合的に提供するための計画です。
この計画の実現に向けて、新潟市は、地域住民や関係機関と連携し、今後も様々な取り組みを進めていく予定です。
3.訪問看護・介護の充実
新潟市地域包括ケア計画では、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、訪問看護・介護の充実を図ることが重要な柱の一つとなっています。
なぜ訪問看護・介護の充実が必要なのか?
- 高齢化の進展: 日本社会全体が少子高齢化が進み、新潟市においても高齢者の割合が増加しています。これに伴い、要介護状態の高齢者が増加し、在宅での生活を支えるための訪問看護・介護の需要が高まっています。
- 地域包括ケアシステムの構築: 新潟市は、地域包括ケアシステムの構築を進めており、医療機関、介護サービス事業所、住民などが連携し、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせる環境づくりを目指しています。このシステムにおいて、訪問看護・介護は、医療と介護の連携を強化し、切れ目のないサービスを提供する上で重要な役割を担います。
- 在宅医療・介護の推進: 高齢者は、可能な限り住み慣れた地域で自分らしく暮らしたいという希望を持つことが多いです。訪問看護・介護の充実により、在宅での医療・介護サービスの提供が強化され、高齢者の在宅生活をサポートすることができます。
新潟市地域包括ケア計画における訪問看護・介護の充実に向けた取り組み
新潟市では、訪問看護・介護の充実に向けて、以下の様な取り組みが行われています。
- 訪問看護ステーションの増設: 訪問看護ステーションの数を増やし、より多くの人々に訪問看護サービスを提供できるようにしています。
- 多職種連携の強化: 医師、看護師、介護福祉士、理学療法士など、様々な専門職が連携し、一人ひとりの高齢者に合わせたケアを提供できる体制を構築しています。
- 在宅医療・介護支援センターの機能強化: 在宅医療・介護支援センターは、在宅での医療・介護に関する相談窓口として、利用者のニーズに合ったサービスを提供しています。
- 介護予防事業の充実: 高齢者の要介護状態の進行を予防するため、介護予防事業を充実させ、早期からの支援を行っています。
- 地域住民の参加促進: 地域住民が、高齢者の生活を支える活動に参加できるよう、様々な取り組みを行っています。
訪問看護・介護の充実がもたらす効果
訪問看護・介護の充実により、以下の様な効果が期待できます。
- 高齢者の生活の質の向上: 高齢者が、住み慣れた地域で安心して暮らせるようになり、生活の質が向上します。
- 医療費の抑制: 早期からの支援により、重症化を防ぎ、医療費の抑制につながることが期待されます。
- 地域社会の活性化: 地域住民が、高齢者の生活を支える活動に参加することで、地域社会の活性化につながります。
今後の課題
- 人材不足: 訪問看護・介護の分野では、人材不足が深刻な問題となっています。人材確保と育成が喫緊の課題です。
- サービスの質の向上: より質の高いサービスを提供するために、従事者の専門性の向上や、サービスの評価ku体制の整備が求められます。
- 地域住民の意識改革: 地域住民が、高齢者の生活を支えることの重要性を理解し、積極的に参加できるよう、意識改革が必要です。
新潟市は、今後も地域包括ケアシステムの構築を推進し、訪問看護・介護の充実を図ることで、高齢者が安心して暮らせる地域社会の実現を目指していきます。
4.地域包括支援センターについて
地域包括支援センターは、地域に住む高齢者の方やそのご家族の方に対して、介護や福祉に関する様々な相談に応じ、必要な支援を行う施設です。2005年の介護保険法改正により設置され、地域の高齢者福祉の向上を目的に活動しています。
地域包括支援センターの役割
地域包括支援センターは、大きく分けて以下の4つの役割を担っています。
- 総合相談・支援
- 介護サービスに関する相談
- 医療機関との連携
- 生活に関する相談(住まい、経済など)
- 権利擁護(虐待防止など)
- 介護予防に関する相談
- その他、高齢者に関するあらゆる相談
- 介護予防ケアマネジメント
- 要支援1・2と認定された方に対して、介護予防のためのケアプランを作成し、サービスを提供します。
- 包括的・継続的ケアマネジメント
- 要介護認定を受けた方に対して、ケアプランを作成し、サービスを提供します。
- 地域の支援体制づくり
- 地域の医療・介護・福祉サービスに関する情報提供
- 地域住民への啓発活動
- 地域の多様な主体との連携
地域包括支援センターの利用方法
地域包括支援センターの利用は、原則として無料です。相談したい方は、直接センターに電話または窓口で問い合わせてください。
地域包括支援センターで相談できること
- 介護サービスの種類や選び方
- 介護保険の手続き
- 在宅での介護について
- 高齢者の住宅改修
- 高齢者の医療機関への紹介
- 高齢者の心のケア
- 高齢者の権利擁護
- 介護予防について
- その他、高齢者に関するあらゆること
地域包括支援センターの職員
地域包括支援センターには、様々な専門職が配置されています。
- 主任ケアマネジャー: 介護保険サービス計画の作成や、サービスの調整を行います。
- 社会福祉士: 相談支援や、地域住民との連携を行います。
- 保健師: 健康に関する相談や、予防策の提案を行います。
- 栄養士: 食事に関する相談や、栄養指導を行います。
5.秋葉区の地域包括支援センターの活動
秋葉区には、地域包括支援センターが複数あり、高齢者の方々やそのご家族に対する様々な支援を行っています。介護に関する相談、ケアプランの作成、訪問サービス、地域活動支援など、幅広いサービスを提供しています。特に、地域住民との連携を重視しており、高齢者の方々が安心して暮らせる地域作りを推進しています。
地域包括支援センターを核とした連携
地域包括支援センターは、この連携の中心的な役割を担っています。各センターでは、以下の様な活動を行っています。
- 多職種連携会議: 医師、看護師、介護福祉士、ケアマネジャー、栄養士など、様々な職種の専門家が定期的に集まり、個々の高齢者の状況を共有し、適切な支援策を検討します。
- 地域ケア会議: 医療機関、介護施設、福祉施設だけでなく、地域住民やボランティアなど、多様な主体が参加し、地域全体で高齢者を支えるための取り組みについて話し合います。
- 情報交換: 地域の医療・介護・福祉に関する情報を共有し、連携を強化します。
- 地域住民への啓発: 高齢者に関する正しい知識や、地域での支援体制について地域住民に広く伝えるための活動を行います。
地域での具体的な取り組み例
- 訪問看護ステーションとの連携: 訪問看護ステーションと連携し、自宅で療養している高齢者への訪問看護サービスを提供することで、入院を予防したり、早期退院を支援したりします。
- 介護施設との連携: 介護施設と連携し、施設入所前の相談や、退院後の受け入れなど、切れ目のないサービスを提供します。
- 地域住民との連携: 地域住民向けの健康教室や介護予防体操を開催したり、ボランティアを募集したりすることで、地域全体で高齢者を支える体制を構築します。
- 他の行政機関との連携: 市役所、消防署、警察署など、他の行政機関と連携し、高齢者の安全確保に努めます。
地域コミュニティの活性化とICT
秋葉区では、ICTを活用して地域コミュニティを活性化させる取り組みも進んでいます。
- 地域情報サイト: 地域の情報やイベントなどを発信するウェブサイトやSNSが多数存在します。これらのプラットフォームを通じて、地域の最新情報を入手したり、他の住民と交流したりすることができます。
- オンラインコミュニティ: 移住者向けのオンラインコミュニティでは、地域の情報を共有したり、困ったときに相談したりすることができます。オンライン上でつながることで、地域へのスムーズな馴染みが期待できます。
- スマート農業: 農業分野においても、ICTを活用したスマート農業が導入されています。ドローンやセンサーを利用して、効率的な農業を実現する取り組みが進んでいます。
将来的なICT活用の可能性
- スマートシティ: 秋葉区は、今後、スマートシティ化が進む可能性があります。スマートシティでは、IoT技術を活用して、街のインフラを効率的に管理したり、住民の生活をより快適にすることが目指されています。
- 遠隔医療: ICTを活用することで、遠隔医療がより身近なものとなる可能性があります。自宅にいながら医師の診察を受けられるようになれば、医療へのアクセスが向上します。
6.秋葉区における地域包括支援センターの具体的な対応
秋葉区の地域包括支援センターでは、地域の高齢者の方々が安心して暮らせるよう、様々な支援を行っています。以下に、具体的な対応事例をいくつかご紹介します。
1. 個別相談
- 介護サービスに関する相談:
- どの介護サービスが必要か、どの事業所が自分に合っているかなど、一人ひとりの状況に合わせて最適なサービスを提案します。
- 介護保険の手続きや費用に関する疑問にも丁寧に対応します。
- 医療に関する相談:
- 医療機関の紹介、医療費の相談、在宅医療に関する相談など、医療に関する様々な相談に対応します。
- 住まいに関する相談:
- 住宅改修や、高齢者向けの住宅への転居など、住まいに関する相談にも対応します。
- 経済的な相談:
- 高齢者向けの福祉サービスや、生活費に関する相談に対応します。
- 心のケア:
- 介護疲れや孤独感など、心の悩みを抱えている方に対して、傾聴やアドバイスを行います。
2. ケアプランの作成
- 要介護認定を受けた方: 介護が必要な度合いを評価し、その人に合った介護サービス計画(ケアプラン)を作成します。
- 要支援認定を受けた方: 介護予防のためのケアプランを作成し、生活習慣の改善や、介護予防サービスの利用を支援します。
3. 地域との連携
- 医療機関: 医師や看護師と連携し、在宅医療の推進や、急な病気やケガへの対応を行います。
- 介護施設: 介護施設と連携し、施設入所前の相談や、退院後の受け入れなど、切れ目のないサービスを提供します。
- 地域住民: 地域住民向けの健康教室や介護予防体操を開催したり、ボランティアを募集したりすることで、地域全体で高齢者を支える体制を構築します。
- 他の行政機関: 市役所、消防署、警察署など、他の行政機関と連携し、高齢者の安全確保に努めます。
4. 地域包括ケアシステムの推進
秋葉区では、地域包括支援センターを中心に、医療、介護、福祉、住まい、生活支援などが一体となって、高齢者が住み慣れた地域で安心して暮らせるよう、地域包括ケアシステムの構築を目指しています。
秋葉区ならではの取り組み
秋葉区の地域包括支援センターでは、地域の特徴や住民のニーズに合わせて、様々な取り組みを行っています。例えば、
- 地域住民向けの健康教室: 地域の集会所や公民館などで、健康に関する講座や体操教室を開催しています。
- 認知症カフェ: 認知症の方とその家族が気軽に集まれる場所を提供し、情報交換や交流の場を設けています。
- ボランティアの育成: 地域住民を対象としたボランティア養成講座を開催し、地域での支援活動を活性化しています。
秋葉区の地域包括支援センターの探し方
秋葉区の地域包括支援センターの所在地や連絡先については、新潟市ホームページや、お住まいの地域の公民館などでご確認ください。
7.秋葉区地域福祉計画・地域福祉活動計画(2021~2026)
区民一人ひとりが主体的に地域の生活課題に取り組む中で、多くの出会いと気づきを重ねながら住民同士のつながりを深めることを基本とし、お互いを思いやる心、地域でともに助けあい支えあう心、自然にも人にもやさしい心を育み、誰もが笑顔ではつらつと暮らせる地域福祉の展開を目指して定めました。
地域が目指すもの
8.秋葉区の地域分類
旧新津市の区域である「新津地区」と旧小須戸町の区域である「小須戸地区」で構成される。区内の地域は、かつて河川交通が盛んだった時代に栄えた集落も数多く存在する。なお、新津地区は区域が広大であるため、旧新津市の地区割りに準拠し、「新津地区」、「荻川地区」、「満日(まんにち)地区」、「小合(こあい)地区」、「東部地区」、「新関(しんせき)地区」、「金津(かなづ)地区」として記載する。
新津地区
区の中心市街地は新津地区にあり、新津駅東口側を中心とした旧市街には商店街、ショッピングセンターなどがあり、その周りには住宅地が広がる。「鉄道の街」という側面もあって、かつては国鉄職員が駅周辺に数多く居住していた。
国鉄線(当時)沿線で、さらに幹線道路が経由している好立地から、1970年代に入るとかつて「駅裏」と呼ばれていた現在の新津駅西口周辺をはじめ、秋葉山北麓の東新津駅周辺、新津川右岸側の金沢町・新津東町周辺、荻川地域の荻川駅周辺、金津地域の古津駅周辺でも宅地化が進捗。1990年代には新津と荻川の中間に位置する北上地域でも住宅地開発が本格化し、さつき野駅が開設された。これら各地区では現在もなお開発が進められている。
新津地区の地域
新津 (にいつ)
古田 (こだ)
西金沢 (にしかなざわ)
柄目木 (がらめき)
飯柳 (いやなぎ)
田家 (たい)
北上(きたかみ)
下興野(しもごや)
善道(ぜんどう)
荻川地区
東日本旅客鉄道(JR東日本)信越本線荻川駅を中心に市街地が広がり、中野などに大きな集落がある。また信濃川と小阿賀野川の合流点に位置する覚路津は、古くから江南区両川地区と生活圏が近しく、覚路津周辺の加入電話の市外局番は「025」となっている。
荻川地区の地域
結(むすぶ)
川口(かわぐち)
北潟(きたがた)
田島(たじま)
福島(ふくじま)
荻島(おぎじま)
中野(なかの)
車場(くるまば)
市之瀬(いちのせ)
覚路津(かくろづ)
満日(まんにち)地区
地区北部の小阿賀野川左岸側には、七日町などに大きな集落がある。
満日地区の地域
満願寺(まんがんじ)
七日町(なのかまち)
大蔵(だいぞう)
小合地区
地区西部の信濃川右岸側には、子成場などに大きな集落がある。
小合地区の地域
子成場(こなしば)
梅ノ木(うめのき)
出戸(でと)
四ツ興野(よつごや)
蕨曽根(わらびそね)
小屋場(こやば)
浦興野(うらごや)
川根(かわね)
大秋(おおあき)
大鹿(おおじか)
小戸上組(こどかみぐみ)
小戸下組(こどしもぐみ)
栗宮(くりみや)
東部地区
地区東部の阿賀野川左岸側には阿賀浦橋西詰周辺の中新田・大安寺、五泉市と接する下新などに大きな集落がある。
東部地区の地域
大安寺(だいあんじ)
東金沢(ひがしかなざわ)
中新田(なかしんでん)
新関(しんせき)地区
新関地区の地域
下新(しもしん)
大関(おおせき)
岡田(おかだ)
市新(いちしん)
小口(こぐち)
金屋(かなや)
新郷屋(しんごや)
六郷(ろくごう)
牧ヶ鼻(まきがはな)
金津(かなづ)地区
同区南部に位置する金津地区は古くから石油の里として栄えた。現在も石油の世界館を始め多くの遺構が残り当時の様子をうかがうことができる。地区東部の東島地区には新潟薬科大学がありバイオリサーチパークを目指す秋葉区の中心的存在となっている。
金津地区の地域
程島(ほどじま)
中村(なかむら)
西島(にしじま)
東島(ひがしじま)
古津(ふるつ)
朝日(あさひ)
割町(わりまち)
塩谷(しおだに)
金津(かなづ)
蒲ヶ沢(がわけさわ)
小須戸地区
小須戸地区の地域
横川浜(よこがわはま)
水田(すいた)
小向(こむかい)
新保(しんぼ)
竜玄(りゅうげん)
矢代田(やしろだ)
天ヶ沢(あまがさわ)
鎌倉(かまくら)
小須戸市街 (町家が多く残る)
小須戸地区の市街地は大きく分けて2箇所ある。
小須戸
信濃川右岸側に位置し、区役所小須戸出張所が置かれている小須戸(こすど)は、古くから行政・商業の中心地であり、かつては河川交通の要衝でもあった地域。新津地区中心部と南区白根地区中心部のほぼ中間に位置しており、現在でも新津だけでなく、白根とも生活圏を近しくしている。市街地外郭部は一部が新興住宅地、さらにその外郭部は水田や田畑となっている。但し交通の便はあまり良くなく、公共交通はバスのみ。路線バスは小須戸線を経由して新潟市中心部に至る路線と、新津駅から矢代田駅経由で白根中心部を結ぶ路線の2路線と、小須戸から同駅経由で新津駅に至る区バス(後述)の計3路線があるのみで、いずれも運行本数は少ない。また市街地の道路も狭隘で歩道が無い区間も多く、整備・改良が待たれる。
矢代田
もうひとつ市街地を形成しているのが、信越本線と、新津や加茂市、五泉市などに至る幹線道路が経由する矢代田(やしろだ)。1970年代以降は前述の新津地区内の各地域同様、交通の利便性を活かして宅地化が進捗した。駅南東側の丘陵西麓に位置する松ヶ丘や、駅西側の水田を埋め立てて開発された舟戸などがこれに該当する。矢代田駅では橋上駅舎への改築工事が行われており、2008年6月に駅舎と自由通路の仮供用を開始した。今後は新津駅などと共に地区内の交通拠点としての役割が期待されている。矢代田駅から小須戸中心部へは車で約5分。国道403号のバイパス区間(通称小須戸田上バイパス)は2020年3月22日に全線開通した。