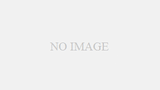▷通院、または、訪問診断で行われる血液検査、尿検査の項目
・実際の計測値がわかれば、すぐに記入
・各検査項目について、ネットで調査した内容を追記
血液検査表
血液検査表説明
血液検査表の各項目について、検査結果照会シートとネットで調査した内容を説明
1. 血液一般
血液細胞の種類や数、大きさなどを調べ、貧血や感染症、出血の有無などを評価します。
① 白血球数
白血球は、体内に侵入した細菌やウイルスなどの異物を攻撃し、体を守る働きをしています。白血球の種類によって、それぞれ異なる役割を担っています。
基準値:30~82 ×10^2/μLr
高値の場合:
・感染症、炎症、アレルギーなど
低値の場合:
・免疫力が低下している状態、骨髄の病気など
② 赤血球数
赤血球は、肺から取り込んだ酸素を体のすみずみの細胞に運ぶ役割を担っています。
基準値:400~520 ×10^4/μL
高値の場合:
・多血症など
低値の場合:
・貧血など
③ ヘモグロビン
ヘモグロビンは、赤血球の中に含まれる赤色の色素で、酸素と結合して体内に運ぶ役割を担っています。
基準値:14~18 g/dL
高値の場合:
・脱水、多血症など
低値の場合:
・貧血、慢性疾患など
④ ヘマトクリット
ヘマトクリットは、血液中の赤血球が占める割合を示します。
基準値:39~50 %
高値の場合:
・脱水、多血症など
低値の場合:
・貧血、出血など
⑤ MCV, MCH, MCHC
これらの項目は、赤血球の大きさやヘモグロビン量に関する情報を与えてくれます。
MCV (平均赤血球容積)
赤血球1個の平均的な大きさ
基準値:88~99 fl
高値の場合:
・大球性貧血(ビタミンB12欠乏性貧血、葉酸欠乏性貧血など)
低値の場合:
・小球性貧血(鉄欠乏性貧血など)
MCH (平均赤血球ヘモグロビン量)
赤血球1個に含まれるヘモグロビンの平均量
基準値:29~35 pg
高値の場合:
・大球性貧血
低値の場合:
・小球性貧血、鉄欠乏性貧血など
MCHC (平均赤血球ヘモグロビン濃度)
赤血球1個あたりのヘモグロビンの濃度
基準値:31~36 %
高値の場合:
・ほとんどの場合、異常はありません
低値の場合:
・小球性貧血、鉄欠乏性貧血など
これらの値を組み合わせることで、貧血の種類をより詳しく診断することができます。
⑥ 血小板数
血小板は、血管が傷ついたときに集まって血栓を作り、出血を止める働きをしています。
基準値:14~40 ×10^4/μL
高値の場合:
・血栓症のリスク上昇
・特発性血小板増加症、悪性腫瘍など
低値の場合:
・出血しやすい状態
・特発性血小板減少性紫斑病、薬剤性血小板減少、肝疾患など
2. 血液像
血液像は、血液中の様々な細胞の種類や数を調べる検査で、体の状態を把握する上で重要な手がかりとなります。
血液には、大きく分けて赤血球、白血球、血小板の3種類が含まれています。血液像を見るのは、白血球の中の顆粒球と呼ばれるグループに属する好塩基球、好酸球、好中球と、リンパ球、単球、そして赤血球の若い細胞である網状赤血球です。
血液像検査では、これらの細胞の種類や数を数えることで、以下のことがわかります。
・感染症: 細菌感染、ウイルス感染、寄生虫感染などが疑われる場合
・アレルギー: アレルギー反応が起きている場合
・炎症: 炎症性の病気がある場合
・血液疾患: 白血病、貧血など
・免疫疾患: 免疫系の異常がある場合
血液には、大きく分けて赤血球、白血球、血小板の3種類が含まれています。血液像を見るのは、白血球の中の顆粒球と呼ばれるグループに属する好塩基球、好酸球、好中球と、リンパ球、単球、そして赤血球の若い細胞である網状赤血球です。
① 好塩基球
アレルギー反応や炎症に関わる。ヘパリンという物質を産生し、血液を固まりにくくする働きがある。
基準値:0~1 %
高値の場合:
・アレルギー性疾患、慢性骨髄性白血病、甲状腺機能低下症など
低値の場合:
・特に明らかな疾患との関連性は少ない
② 好酸球
アレルギー反応や寄生虫感染に関わる。炎症部位に集まり、アレルギー反応を抑えたり、寄生虫を攻撃したりする。
基準値:1~5 %
高値の場合:
・アレルギー性疾患、寄生虫感染症、特定の皮膚疾患、悪性腫瘍など
低値の場合:
・ストレス、コルチコステロイドの使用など
③ 好中球
細菌感染症に対する防御の第一線。細菌を貪食し、殺菌する。
基準値:45~55 %
高値の場合:
・急性細菌感染症、炎症性疾患、悪性腫瘍など
低値の場合:
・骨髄機能低下、重症感染症、コルチコステロイドの使用など
④ リンパ球
免疫反応の中心的役割を担う。ウイルス感染症や腫瘍細胞に対する免疫反応に関わる。
基準値:25~45 %
高値の場合:
・ウイルス感染症、慢性リンパ性白血病、悪性リンパ腫など
低値の場合:
・免疫不全症、コルチコステロイドの使用、悪性リンパ腫など
⑤ 単球
マクロファージへと変化し、異物や老廃物を貪食する。炎症反応や免疫反応に関わる。
基準値:4~7 %
高値の場合:
・結核、慢性炎症性疾患、白血病など
低値の場合:
・骨髄機能低下、コルチコステロイドの使用など
⑥ 網状赤血球
骨髄で作られたばかりの若い赤血球。骨髄の造血機能を評価する指標となる。
基準値:0.5~1.8 %
高値の場合:
・貧血からの回復期、溶血性貧血など
低値の場合:
・骨髄の機能低下、再生不良性貧血など
3. 血液の凝固に関する検査
血液の凝固に関する検査で、互いに関連しながら、血液の凝固状態や出血傾向を評価する上で重要な役割を果たしています。
PT、PT活性%、PT-INR:これらの検査項目は、いずれも外因系の凝固経路に関連しており、互いに関連性の高い検査です。PT-INRは、PTの結果を国際的に標準化された指標に変換したもので、経口抗凝固薬のモニタリングに広く利用されています。
PTとAPTT:PTとAPTTは、ともに凝固時間を測定する検査ですが、評価する凝固経路が異なります。PTは外因系、APTTは内因系を評価するため、両方の検査を行うことで、凝固異常の原因をより詳細に特定することができます。
Dダイマーと他の検査:Dダイマーは、血栓ができたかどうかではなく、血栓が溶けたかどうかの指標です。そのため、Dダイマーが陽性であっても、必ずしも血栓症を意味するわけではありません。Dダイマーが陽性の場合は、さらに詳しい検査(CT、MRIなど)が必要となることがあります。
これらの検査項目は、単独でみるよりも、他の検査結果と総合的に判断することで、より正確な診断が可能になります。例えば、PTとAPTTがともに延長している場合は、広範な凝固因子の異常が疑われます。また、Dダイマーが陽性で、同時にPTやAPTTが異常を示す場合は、血栓症の可能性が高まります。
① プロトロンビン時間(PT)
血液が凝固するまでの時間を測定する検査です。主に、外因系の凝固因子(VII因子、X因子など)の活性や、ビタミンKの欠乏などを評価する際に用いられます。
基準値:10.5~13.0秒
高値の場合:
・肝機能障害: 肝臓で血液凝固因子が十分に作られていない。
・ビタミンK欠乏: ビタミンKは血液凝固に関わる重要な栄養素です。
・凝固因子の先天的な欠乏: 遺伝的な原因で、特定の凝固因子が不足している。
・抗凝固薬の効果: ワルファリンなどの抗凝固薬が効きすぎている。
低値の場合:
・血栓症: 血液が固まりやすくなっている状態。
・炎症: 炎症反応によって血液凝固が促進されることがある
② PT活性%
PTの結果を、健常人の平均値と比較して、その人の凝固能が健常人の何%に相当するかを示す指標です。
基準値:70~120%
高値の場合:
・血液が通常よりも早く固まる可能性があります。
・血栓症のリスクが高まることがあります。
・炎症などの状態が考えられます。
低値の場合:
・血液が通常よりも遅く固まる可能性があります。
・出血しやすい状態が考えられます。
・肝機能障害、ビタミンK欠乏、凝固因子の先天的な欠乏などが考えられます。
③ PT-INR
国際標準化比。PTの結果を国際的に統一された基準で表示するための指標です。経口抗凝固薬(ワーファリンなど)を服用している患者さんの治療効果を評価する際に特に重要です。
基準値:0.85~1.15
高値の場合:
・肝機能障害: 肝臓で血液凝固因子が十分に作られていない。
・ビタミンK欠乏: ビタミンKは血液凝固に関わる重要な栄養素です。
・凝固因子の先天的な欠乏: 遺伝的な原因で、特定の凝固因子が不足している。
・抗凝固薬の効果: ワルファリンなどの抗凝固薬が効きすぎている。
低値の場合:
・血栓症: 血液が固まりやすくなっている状態。
・炎症: 炎症反応によって血液凝固が促進されることがある。
④ APTT
PTと同様に凝固時間を測定する検査ですが、主に内因系の凝固因子(XII因子、XI因子など)の活性や、ヘパリンなどの抗凝固薬の影響を評価する際に用いられます。
基準値:25~40秒
高値の場合:
・血友病: 遺伝性の出血性疾患で、特定の凝固因子が欠乏しています。
・肝機能障害: 肝臓で作られる凝固因子の量が減少している場合。
・ビタミンK欠乏: ビタミンKは血液凝固に関わる重要な栄養素です。
・ヘパリン投与: ヘパリンは血液を固まりにくくする薬であり、APTTを延長させます。
・獲得性凝固異常: 自己抗体などが原因で、凝固因子が阻害される場合。
低値の場合:
・血栓症: 血液が固まりやすくなっている状態。
・炎症: 炎症反応によって血液凝固が促進されることがある。
⑤ 血漿Dダイマー(Dダイマー)
血栓が溶けた際に生じる分解産物で、血栓症の診断に有用なマーカーです。
基準値:1以下 μg / ml
高値の場合:
・血栓症: DVT、PE、DICなどが疑われます。
・悪性腫瘍: 特に進行したがんでは、Dダイマーが高くなることがあります。
・炎症性疾患: 関節リウマチや炎症性腸疾患など、炎症が強い状態でもDダイマーは上昇することがあります。
・妊娠: 妊娠中は、生理的な変化によってDダイマーが上昇することがあります。
低値の場合:
・一般的に、Dダイマーが低い場合は特に問題ありません。しかし、血栓症が疑われるにも関わらずDダイマーが低い場合は、他の原因が考えられます。
4. 尿検査
腎臓の働きや尿路の異常を調べるための検査です。
尿検査の「乳び」や「溶血」の言葉は、尿の見た目の特徴を表しており、病気の診断に役立つことがあります。
尿検査で乳びや溶血が見られることは、必ずしも病気のサインとは限りません。しかし、これらの症状は、腎臓病や尿路の病気などの可能性を示唆しているため、注意が必要です。
① 乳び(ZS)
乳びとは、尿が白く濁って牛乳のように見える状態を指します。これは、尿中に脂肪分が多く含まれているために起こります。
検出時:
・腎臓病: ネフローゼ症候群など、腎臓の病気によって尿中に蛋白や脂肪が漏出することがあります。
・リンパ系の病気: リンパ管の病気で、リンパ液が尿中に混ざることもあります。
・過度の運動: 激しい運動後には、一時的に乳びが見られることがあります。
・食後の尿: 脂肪分の多い食事をした直後の尿では、乳びが見られることがあります。
② 溶血(ZS)
溶血とは、尿が赤色を帯びている状態を指します。これは、赤血球が壊れて、その中のヘモグロビンが尿中に漏出するためです。
検出時:
・腎臓病: 糸球体腎炎など、腎臓の病気によって赤血球が尿中に漏出することがあります。
・尿路結石: 尿路に結石ができ、尿道が傷ついて出血することがあります。
・感染症: 尿路感染症など、尿路の感染によって出血することがあります。
・運動: 激しい運動後には、一時的に溶血が見られることがあります。
5. 生化学検査
血中にある様々な物質の濃度を測定し、肝機能、腎機能、血糖値、脂質異常症など、様々な臓器の働きや代謝状態を評価します。
血液検査の生化学検査は、血液中の様々な成分を測定することで、体の状態を詳しく把握する検査です。
■腎臓の働きを評価する項目
・尿素窒素(BUN)
・クレアチニン
・eGFR
・Na(ナトリウム)、K(カリウム)、Cl(塩素)
腎臓に関するいろいろ | ADPKD.JP ~多発性嚢胞腎についてよくわかるサイト~ | 大塚製薬
腎臓病の症状 | 腎臓が悪くなると出てくる「各症状」のいろいろを知ろう
■肝臓の働きを評価する項目
・GOT(AST)、GPT(ALT)
・ALP(IFCC)
・γ-GTP
・LD(IFCC)
・総ビリルビン、直接ビリルビン
■その他の項目
・カルシウム
・CK
・アミラーゼ
・アルブミン、総蛋白
・CRP
■腫瘍マーカー
腫瘍マーカーとは、がん細胞が作り出す物質や、がん細胞によって誘導される物質のことで、血液中に現れることがあります
腫瘍マーカーは、あくまでも補助的な検査であり、がんの診断を確定するためには、画像検査(CT、MRIなど)や内視鏡検査など、他の検査との組み合わせが必要です。
・CEA
・CA19-9
① 尿素窒素(BUN)
腎臓で尿素が生成され、血液から尿中に排泄されます。BUNの上昇は、腎機能の低下を示すことがあります。
基準値:8~20 mg/dL
高値の場合:
・腎機能低下、脱水、高タンパク食など 低値の場合:
・肝硬変、栄養不良など
② クレアチニン
筋肉で生成され、腎臓で排泄されます。クレアチニンの上昇も、腎機能の低下を示す重要な指標です。
基準値:0.65~1.07 mg/dL
高値の場合:
・腎機能低下、筋肉量の多い人、脱水など 低値の場合:
・筋肉量が少ない人
③尿酸
細胞の代謝産物
基準値:4.5~7.0 mg/dL
高値の場合:
・痛風、腎臓病、高血圧など
低値の場合:
・特になし
④ eGFR
腎臓の糸球体濾過率を推定する値で、腎機能の程度を表します。数値が低いほど、腎機能が低下していることを示します。
基準値:
90mL/分/1.73m²以上: 正常範囲
60~89mL/分/1.73m²: 軽度の腎機能低下
30~59mL/分/1.73m²: 中程度の腎機能低下
15~29mL/分/1.73m²: 重度の腎機能低下
15mL/分/1.73m²未満: 腎不全
高値の場合:
・腎機能が正常
低値の場合:
・腎機能低下
⑤ Na(ナトリウム)、K(カリウム)、Cl(塩素)
電解質と呼ばれるミネラルで、体内の水分バランスや神経の働きに重要な役割を果たします。腎臓は、これらの電解質のバランスを調節する働きがあります。
Na(ナトリウム)
基準値:136~152 mEq/l
高値の場合:
・脱水、腎臓病、副腎皮質ホルモンの分泌過多など
低値の場合:
・腎臓病、下痢、嘔吐など
K(カリウム)
基準値:3.5~5.0 mEq/I
高値の場合:
・脱水、腎臓病、副腎皮質ホルモンの分泌低下など
低値の場合:
・腎臓病、下痢、嘔吐など
Cl(塩素)
基準値:101~110 mEq/I
高値の場合:
・脱水
低値の場合:
・嘔吐、下痢など
⑥ GOT(AST)、GPT(ALT)
肝細胞に多く含まれる酵素で、肝細胞が損傷を受けると血液中に漏れ出てきます。これらの酵素の上昇は、肝炎や肝硬変などの肝臓の病気の指標となります。
GOT(AST)
基準値:10~28 U/L
高値の場合:
・肝炎、心筋梗塞、筋肉の病気など
低値の場合:
・特になし
GPT(ALT)
基準値:4~30 U/L
高値の場合:
・肝炎
低値の場合:
・特になし
⑦ ALP(IFCC)
肝臓や骨などに多く含まれる酵素で、胆道閉塞や骨の病気などで上昇することがあります。
基準値:38~113 U/L
高値の場合:
・肝疾患、骨の病気、妊娠など
低値の場合:
・特になし
⑧ γ-GTP
肝臓や胆道に多く含まれる酵素で、アルコール摂取や肝臓の病気で上昇することがあります。
基準値:10~60 U/L
高値の場合:
・肝疾患、アルコール摂取など
低値の場合:
・特になし
⑨ LD(IFCC)
多くの臓器に含まれる酵素で、肝臓の病気のほか、心筋梗塞や悪性腫瘍でも上昇することがあります。
基準値:124~222 U/L
高値の場合:
・肝疾患、心疾患、悪性腫瘍など
低値の場合:
・特になし
⑩ 総ビリルビン
赤血球が壊れる際にできる物質で、肝臓で処理されます。これらの値の上昇は、肝炎や胆道閉塞などの肝臓の病気の指標となります。
基準値:0.2~1.2 mg/dL
高値の場合:
・肝炎、胆道閉塞など
低値の場合:
・特になし
⑪ 直接ビリルビン
総ビリルビンのうち、肝臓でグルクロン酸と結合した成分
基準値:0~0.2 mg/dL
高値の場合:
・肝炎、胆道閉塞など
低値の場合:
・特になし
⑫ カルシウム
骨や歯の成分であり、神経や筋肉の働きにも重要です。
基準値:8.5~10.2 mg/dL
高値の場合:
・甲状腺機能亢進症、悪性腫瘍など
低値の場合:
・低カルシウム血症(副甲状腺機能低下症、ビタミンD欠乏症など)
⑬ CK
筋肉に多く含まれる酵素で、心筋梗塞や筋肉の病気で上昇することがあります。
基準値:29~203 U/L
高値の場合:
・心筋梗塞、筋肉の病気など
低値の場合:
・特になし
⑭ アミラーゼ
膵臓に多く含まれる酵素で、膵炎で上昇することがあります。
基準値:43~116 U/L
高値の場合:
・膵炎、唾液腺の病気など
低値の場合:
・特になし
⑮ アルブミン
肝臓で作られるタンパク質で、栄養状態や肝機能の指標となります。
基準値:3.9~4.9 g/dL
高値の場合:
・脱水、慢性疾患など
低値の場合:
・肝疾患、腎疾患、栄養不良など
⑯ 総蛋白
血漿中のタンパク質の総量
基準値:6.7~8.3 g/dL
高値の場合:
・脱水、多発性骨髄腫など
低値の場合:
・肝疾患、腎疾患、栄養不良など
⑰ CRP
体内に炎症があるときに増加するタンパク質で、感染症や炎症性疾患の指標となります。
基準値:0.30 以下 mg/dL
高値の場合:
・感染症、炎症性疾患など
低値の場合:
・特になし
⑱ CEA
さまざまな種類の癌で上昇することがあります。
特に大腸がん、肺がん、胃がん、乳がん、膵臓がんなどでよく調べられます。
がんの診断だけでなく、治療効果の判定や再発の監視にも利用されます。
基準値:5.0 ng/mL以下
⑲ CA19-9
主に膵臓がん、胆道がん、大腸がん、胃がんの診断に用いられます。
CEAと同様に、治療効果の判定や再発の監視にも利用されます。
基準値:37.0 U/mL以下
6. その他
① 血糖値
血液中のブドウ糖の濃度で、糖尿病の診断や治療効果の判定に用いられます。
『食前の目標範囲』:70 mg/dL〜130 mg/dL
『食後の目標範囲』: 70 mg/dL〜180 mg/dL
高値の場合:
・糖尿病、糖尿病予備群、ストレス、感染症、ホルモン異常など
低値の場合:
・インスリン過剰、肝機能障害、栄養不良など
② 食事時間
前の食事から血液検査までの時間
食事時間は、直接的に好中球数やリンパ球数に影響を与えるわけではありません。しかし、食事によって血糖値や脂質などの血液成分が変化し、間接的にこれらの数値に影響を与える可能性はあります。
血糖値: 食事後には血糖値が上昇します。血糖値は、糖尿病などの診断に重要な指標となるため、空腹時の血糖値を測定することが一般的です。
脂質: 食事によって血中の脂質濃度が上昇し、脂質異常症などの診断に影響を与える可能性があります。
その他: 食事によって、肝機能や腎機能に関わる検査値も変動することがあります。
一般的に、血液検査前の食事制限は、8時間以上の絶食が求められることが多いです。
③ 好中球数
好中球は、白血球の一種で、細菌感染に対して最初に反応し、体を守る働きをしています。
基準値:15 x10^2/μL以上: 正常範囲
一般的には18~75 x10^2/μL/μL
高値の場合:
・細菌感染: 肺炎、腎盂腎炎など
・炎症: リウマチ、痛風など
・ストレス: 外傷、手術など
低値の場合:
・骨髄の病気: 白血病など
・薬の副作用: 抗がん剤など
・重症感染症: 敗血症など
感染しやすい・白血球減少
好中球減少症
10以下の場合、化学療法点滴は中止
④ リンパ球数
リンパ球は、ウイルス感染やがん細胞に対する免疫反応の中心的な役割を担っています。
基準値:10~48 x10^2/μL/μL
高値の場合:
・ウイルス感染: インフルエンザ、風疹など
・リンパ腫: リンパ系の悪性腫瘍
・慢性リンパ性白血病
低値の場合:
・免疫不全症: エイズなど
・ステロイド剤の長期使用
・リンパ球減少症
⑤ HbA1c (NGSP)
HbA1c(ヘモグロビンエーワンシー)は、過去2~3ヶ月の間の平均的な血糖値を反映する検査です。赤血球中のヘモグロビンというタンパク質に、血糖値が高い状態が続くと糖がくっつき、HbA1cという物質ができます。このHbA1cの量を測ることで、血糖コントロールの状態を評価することができます。NGSP値とは、HbA1cの国際標準値です。
基準値:4.6~6.2%
高値の場合:
・血糖コントロールが悪い: 血糖値が頻繁に高くなっている可能性があります。
・糖尿病の合併症リスクが高い: 心血管疾患、腎臓病などのリスクが高まります。
低値の場合:
・低血糖: インスリンの分泌過多や、糖尿病治療薬の飲み過ぎ
・赤血球の寿命が短い: 出血や溶血性貧血など、赤血球が早く壊れてしまう状態
・異常なヘモグロビン: 稀なケースですが、遺伝的な要因などにより、ヘモグロビンに異常がある場合