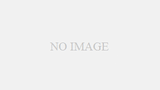末期がんについて、ネットで勉強したので、公開する
参照ページ
①がん終末期の経過・余命1ヶ月の症状や身体機能の低下の具体例とは? | がん免疫療法コラム | 福岡同仁クリニック
https://dojin.clinic/column/3241/
②末期がん余命1ヶ月の症状「詳細な解説と対処法」
https://gan-medical-chiryou.com/cancer-knowledge/1-month-left-to-live-cancer-symptoms/
➂末期がんによく見られる症状とは?急に悪化するのは死の兆候?
https://chibanaika-clinic.com/2024/03/makkigan/
④末期がんの本当に最後の症状と最期の様子と家族のすること【2020年版の専門医解説
https://soukikanwa.jp/home/terminal-cancer-symptom/
➄膵臓がん末期の症状、余命や5年生存率、治療法など詳しく解説
https://dojin.clinic/column/4561/
がん終末期の経過・余命1ヶ月の症状や身体機能の低下の具体例とは?
1. 末期がんで余命1ヶ月~終末期の経過や症状について
末期がんで余命1ヶ月の宣告を受けた場合、身体の状態は急速に変化します。亡くなる約1ヶ月前には、食欲不振や倦怠感、呼吸困難感などの症状が出現し、これらの症状は日を追うごとに増強していく傾向があります。
多くの場合、がんが進行しても患者様の全身状態はしばらくの間保たれています。しかし、死亡が近づく約1ヶ月の間に、その全身状態が急速に低下するのが特徴的です。これは、がんの部位や組織の種類にかかわらず見られる現象で、末期がん患者様の臨床経過には一定の共通性や規則性が存在します。この共通性は、がんが進行するにつれてさらに顕著となる傾向にあり、終末期においては特に明瞭となります。
2. 終末期における【月単位】の経過と症状
余命宣告を受けた際の患者様の身体的・心理的経過は、病状の進行度合いと深く関わっています。特に余命が約1ヶ月と診断された段階と、それを過ぎた後の1ヶ月では、その変化は顕著となります。
余命宣告を受けてから約1ヶ月までの間、多くの患者様は食事の量や水分摂取が徐々に減少していくことが確認されています。これは、がんの進行や腫瘍による通過障害、便秘、嘔吐、嘔気などが影響していると考えられます。また、これらの身体的な症状とともに、心因性の食欲不振も出現することが多いです。
そして、余命宣告から1ヶ月を過ぎると、身体のだるさが増してくることが多くの患者様で確認されています。これは、がんそのものの症状や治療、薬剤の副作用などが主な原因として挙げられます。特に動く度に息が上がるような状態となり、これがさらに不眠や不安、落ち込みなどの心理的症状を引き起こすことも少なくありません。
3. 終末期における【週単位】の経過と症状
がんの進行や機能の衰退に伴い、飲み込む力が次第に弱くなることが多くの患者様で確認されます。この影響で食事量や水分摂取が減少し、体力や筋力の低下が急速に進行します。水分摂取の減少は、脱水状態を引き起こし、それがさらに心臓や腎臓の機能衰えと関連し、尿の量も減少するという状況となります。
また、生存期間が約1週間前頃を迎えると、身体機能の全般的な低下が見られ、患者様は長時間眠るようになります。この時期には、会話するエネルギーも限られ、患者様とのコミュニケーションは少なくなる傾向が強まります。
さらに、約2週間前には「せん妄」という症状が現れることがあります。せん妄は、身体的異常や薬物が原因で急激に発症する意識障害の一つです。主な症状としては、幻覚、妄想、見当識障害、気分の変動や落ち着かない状態などが挙げられます。その背後には、低酸素状態や代謝異常、薬物の影響などによって、脳からの神経伝達物質のバランスが崩れることが関係しています。
4. 終末期における【数日から数時間】の経過と症状
宣告された期間までの数日〜数時間では、患者様はウトウトと眠っている時間が増えるようになります。これは意識の低下を示すもので、苦痛も感じづらくなる一方で、音や声は最後まで聞こえていることが多いので、家族や介護者の声かけに反応することがあります。
また、気道に痰や唾液が溜まる「喘鳴」という症状が見られるようになります。これは筋力の衰えや、咽頭や喉頭の機能の低下により、唾液を適切に飲み込むことができなくなるためで、呼吸の度にゴロゴロとした音が発生します。さらに、胸郭の動きが小さくなり、下顎を使った「下顎呼吸」が見られるようになることもあります。
血液の酸素が不足すると、皮膚が青紫色になる「チアノーゼ」という症状が出現します。これは正常に呼吸を行えないために発生します。
そして、心臓の機能低下が進行すると、脈が触れにくくなるとともに、血圧も低下していきます。この状態は体の生命活動が弱まっていることを示しています。
5. まとめ
死が近付く事は患者様本人やご家族様にとってとてもつらい事です。中には「その様な事は考えたくない」と受け止められない方もいるかもしれません。経過には個人差や予期せぬ急変も大いにあります。これらの症状や機能の衰えは身体が死に向かっている事を意味します。そのため事前に知る事で心構えになり「それからどうするか?」など自分なりに考えやすくなります。
末期がん余命1ヶ月の症状「詳細な解説と対処法」
1. 体力の低下とその背後にある理由
がんの進行に伴い、患者様の体力が著しく低下します。
がん細胞が体内の栄養を奪取し、正常な細胞の機能を妨げるためです。
さらに、がん細胞は急速に増殖し、健康な細胞を圧迫します。
この結果、筋肉の萎縮や全身の疲労感が強まります。
日常生活の動作が困難になり、ベッドでの安静が必要となることが多くなります。
2. 食欲の喪失とその影響
がんの進行により、食欲が減退することが一般的です。
これは、腫瘍が消化器系に影響を及ぼすことや、薬剤の副作用などが原因となります。
食事の量が減少することで、栄養状態が悪化し、さらなる体力の低下を引き起こす可能性があります。
また、食欲の喪失は、患者様の心理的なストレスや不安を増加させる要因ともなります。
適切な栄養補給や食事の工夫が求められます。
3. 呼吸困難とその原因
がんが肺や胸部に広がると、呼吸困難が生じることがあります。
これは、腫瘍が肺の機能を圧迫することや、液体が胸部に溜まることが原因となります。
また、がん細胞が気道を塞ぐことで、呼吸の障害が生じることもあります。
酸素吸入や薬剤の投与が必要となる場合があります。
呼吸のサポートを受けることで、快適な生活を維持することが可能です。
4. 疼痛とその管理
がんの進行に伴い、疼痛を伴うことが増えます。
腫瘍が神経や骨を圧迫することで、激しい痛みが生じることがあります。
疼痛の管理は、専門の医師や看護師との連携が必要となります。
痛みを和らげるための薬剤の投与や、リラクゼーション法などの非薬物療法が提案されることがあります。
疼痛の軽減は、患者様のQOL(生活の質)を向上させるために重要です。
5. 精神的な変化とその対応
余命が短いことを受け入れるのは難しく、患者様の精神的な状態に変化が生じることがあります。
不安や恐怖、抑うつなどの症状が現れることがあります。
心のサポートが必要となる場合があります。
カウンセリングや心理療法を受けることで、精神的な安定を得ることができます。
家族や友人とのコミュニケーションも、心のサポートとして非常に有効です。
6. 対処法とサポートの重要性
末期がんの症状に対する対処は、症状の軽減や患者様のQOL(生活の質)の向上を目指します。
疼痛管理や栄養サポート、心のケアなど、多岐にわたるサポートが必要となります。
専門家との連携を通じて、最良のケアを受けることが大切です。
家族やケアチームとの連携も、患者様の安心感や安全性を高めるために重要です。
適切なケアとサポートにより、患者様の生活の質を最大限に保つことが可能です。
末期がんの症状は、患者様やその家族にとって非常に困難な時期です。
しかし、適切なサポートとケアにより、患者様の苦痛を軽減し、より良い日々を過ごすことが可能です。
専門家との連携を深め、最善のケアを受けることを心がけましょう。
末期がんによく見られる症状とは?急に悪化するのは死の兆候?
■末期がんによくみられる症状
末期がんの患者様が最後の2〜3ヶ月の間に経験する可能性がある症状は多岐にわたります。
これらの症状は、がんの種類、がんが体のどの部分に影響を及ぼしているか、および患者様の全体的な健康状態によって異なります。
以下に、一般的な経過として見られる症状を時系列に沿って説明しましょう。
なお、この説明は一般的な傾向に基づいており、個々の患者様の状況によって異なることをご理解ください。
1. 末期がんの一般的な症状の経過
初期段階(約2~3ヶ月前)
・疲労感
極度の疲労や体力の低下が見られます。
少しの活動(立ったり、歩いたり)でも疲れやすくなります。
・食欲不振
食べることに対する興味が減少し、徐々に体重が減り、痩せていきます。
・痛み
がんの進行によって新たな痛みが現れるか、現在の痛みがさらに悪化することがあります。
・呼吸困難
肺や周囲の組織にがんが広がっている場合、呼吸困難の症状が出現し呼吸がしにくくなることがあります。
中期段階(約1~2ヶ月前)
・意識の変化
寝ている時間が長くなったり、意識が朦朧とする時間が増えたりします。
・浮腫の増悪
足や腹部に浮腫ができ始め、体動困難や不快感を引き起こすことがあります。
・皮膚の変化
黄疸や皮膚の色素沈着など、皮膚に変化が見られることがあります。
末期段階(最後の数週間)
・意識レベルの低下
患者様は大半の時間を眠って過ごし、起きている時も反応が鈍くなります。
摂食・摂水の困難: 飲み込む力が弱まり、食事や水分の摂取が困難になります。
・呼吸パターンの変化
呼吸が徐々に不規則になり、無呼吸の時間が伸びたり、「チェーンストークス呼吸」と呼ばれる呼吸パターンが見られることがあります。
■診断されてからの平均余命は?
末期がん(治療不可能ながん)の患者様の平均余命は、以下などの多くの要因によって大きく異なります。
・がんの種類
・がんの進行度
・患者さんの一般的な健康状態
・利用可能な治療法や緩和ケアの対応
そのため、一概に「すべての末期がん患者の平均余命はこれだ」と示すことは困難です。
1. がんの種類による違い
各種がんにおける進行段階や治療の応答性には大きな差があり、それによって余命も大きく異なります。
例えば、進行した肺がんや膵臓がんの患者様は、比較的短い平均余命を示すことが多いです。
一方で、乳がんや前立腺がんのように、比較的治療の選択肢が多く、ある程度の期間、病状の管理が可能な場合もあります。
以下に末期がんと診断された場合の癌の種類それぞれの平均的な余命を記載します。(個人差があります。)
・進行性非小細胞肺がん
余命は数ヶ月から1年未満の場合が多いです。
・膵臓がん
末期の場合、平均余命は数ヶ月とされます。
・進行性肝臓がん
余命は数ヶ月から1年程度です。
・進行性膠芽腫(脳腫瘍)
数ヶ月から1年程度の余命となることが一般的です。
2. 緩和ケアの役割
末期がん患者様にとって、緩和ケアは症状の管理と生活の質の向上を目的として重要です。
緩和ケアが適切に提供されることで、痛みや呼吸苦などの他の症状が軽減され、患者様とその家族の精神的なサポートが行われます。
これにより、患者様の余命が延長する可能性もありますが、主に生活の質(QOL=Quality of life)の改善に焦点を当てています。
■末期がんと診断されたら?
末期がんと診断された際には、患者様とその家族は多くの選択肢を検討・考慮する必要があります。
治療の目標は、生存期間の延長、症状の緩和、生活の質の向上など、患者様の希望や状態に応じて異なります。
主な選択肢には以下などがあるでしょう。
・諦めず治療を継続する
・緩和ケアへ移行する
・ホスピスケアを受ける
ここではそれぞれのその概要を説明します。
1. 諦めず治療を継続する
末期がんであっても、先進的な治療を選択することは可能です。
これには、がんの進行を遅らせるための化学療法、放射線療法、標的療法、免疫療法などが含まれます。
治療を継続する目的は、可能な限り生存期間を延長することや、症状を管理して生活の質を維持することにあります。
しかし、これらの治療は様々な副作用が伴うことが多く、治療の利益とリスク(メリットとデメリット)を慎重に検討する必要があるでしょう。
2. 緩和ケアへ移行する
緩和ケアは、末期がん患者様の痛みや他の症状を管理し、患者様とその家族に精神的、社会的サポートを提供することに焦点を当てたアプローチです。
緩和ケアの目的は、治療による延命ではなく、患者様の生活の質を最大限に向上させることにあります。
緩和ケアは、以下で受けることができます。
・病院
・緩和ケア専門施設
・在宅
緩和ケアチームは、痛みや不快感の管理、心理社会的な支援、終末期の計画など、患者様とそのご家族様の包括的なニーズに対応します。
3. ホスピスケアを受ける
ホスピスケアは、余命が限られている患者様に対して、緩和ケアの原則に基づいたサポートを提供するサービスです。
ホスピスケアは、治療の目的が延命ではなく、患者様の残された時間をできるだけ快適に過ごすことに重点を置いています。
ホスピスケアは、病院のホスピス病棟、ホスピス専門施設、または患者様の自宅で提供されることが多く、痛みや不快な症状の管理、心理的・精神的な支援、家族へのケアなどを含みます。
また、ホスピスケアチームには、医師、看護師、社会福祉士、精神的支援を提供する専門家など、多職種のスタッフがいます。
これらの選択肢は相互に排他的ではなく、病状の進行に応じて、治療方針を調整することが可能です。
例えば、先進治療を試みた後に、緩和ケアやホスピスケアに移行することも一般的です。
重要なのは、医療従事者が十分な情報とサポートを提供し、患者様とその家族が患者様の価値観や希望に最も合致した選択を行えるようにすることでしょう。
末期がんの本当に最後の症状と最期の様子と家族のすること【2020年版の専門医解説
末期になってからの緩和ケアは絶対的に遅いです。
そうなる前に手を打って、準備をし終える必要があります。
この記事をご覧の皆さんは、末期の状態に興味・関心があったり、あるいはそれを恐れていたり、ご家族がそのような状態に近づきつつあるので、情報を得たい等の様々なお気持ちからだと思います。
まさしくそのような状態の診断と治療の専門家たる緩和ケア専門医(正確には緩和医療専門医)の私が解説します。
なお、2019年3月現在で、緩和医療専門医は全国に208名しかいません(医師数は30万人以上です)。
1. 2011年発表 がん終末期予後判断指
全例に当てはまるわけではないが、予後判断の参考に指針を示す。
がんの場合は、予後2カ月くらいから急速に状態が悪化する。
「悪くなり始めると早い」「悪くなってから色々準備をしても間に合いにくい」
これを医療者間・家族間・場合によっては患者と共有する必要がある。
① 余命短い月単位(余命1~2カ月以内)
・疼痛以外の苦痛症状の出現(疼痛は余命が比較的あるうちから出現するために、あまり予後判断の参考とならない)。例えば全身倦怠感や食欲不振などが出現する。ただしこれらの苦痛症状がステロイドに反応して、ある程度軽減される。また化学療法施行中はその副作用で全身倦怠感や食欲不振などが認められることもあるので、その影響を除いて判定する。
・ADL(日常の立ち居振る舞い)が多少なりとも障害され始める。
・気力の枯渇等から外出が減り、家の中での生活がメインとなる。寝て過ごす時間が多くなる。
・一般的には、「やりたいことを何とかやれる」のはこの時期。例えば最後の旅行など。もう一段階状態が悪化した週単位ではやるべきことをやろうとしても一般に困難になる。在宅移行・転院・一時退院にふさわしい時期。
② 余命短い週単位(余命1~3週間以内)
・疼痛以外の苦痛症状の増悪が認められる。特に全身倦怠感が強くなる。これらの苦痛症状がステロイド投与でも、あまり改善しなくなる。
・ADLの障害が目立ってくる。トイレ歩行も困難になってくる。
・ベッドで臥床している時間が多くを占めるようになる。
・声帯のやせからの嗄声や、耳管の調節機能の低下による耳の異和感や異音の聴取、体力低下に続発する視力低下(ぼやける・かすむなどの表現を取る)などが出現する。
・見当識障害も程度差があるが出現し始める。せん妄・混乱に至る患者も存在する。
・一般的には、「最低限ならば、やり残したことをやれる」限界のライン。外出泊が何とかできる程度。在宅移行・転院・一時退院ができないわけではないが、ぎりぎりの時期。
③ 余命日単位(余命数日以内)
・苦痛症状が一番強くなる。特に全身倦怠感が強くなり★1、身の置き所のないような表現を取ることが多い。また痛いと訴えるが局在がはっきりとせず、身の置き所のなさが「痛い」という表現を取っていることがしばしば認められる。これらの苦痛症状はステロイド投与でも、緩和されない。余命24時間前付近が、苦痛が最大となる時間帯であり、鎮静(最低限間欠的なものでも)を考慮すべき時間帯である。せわしなく体を動かされたり、足が重だるく感じて看護者が動かすのを希望されたりというような表現も目立つ。
・ADLの障害は顕著である。ベッド上から動くことは難しく、また動けないのにトイレへ行こうとして苦しまれることもある。
・表情は一般的に苦悶状。眉間にしわが寄っている。
・寝ているか、あるいは身の置き所のなさ・全身倦怠感で苦しまれるか、というどちらかの状態。
・意思の疎通は通常困難となってくる。せん妄・混乱の頻度も高くなる。
・急変も起こりやすいので、看取りに居合わせたい家族はなるべくそばにいたほうが良い。
④ 余命時間単位(余命1日以内。ほぼ数時間程度。一般の表現で“時間の問題”)
・意識レベルが低下し、苦痛症状を訴えなくなる。
・体動が消失する。
・苦悶状の表情がなくなる。眉間からしわの消失。
・声漏れ(強い息に伴うアーアーの間欠的発声)が出る。これは辛さのためではない。家族に伝える必要がある。
・死前喘鳴(咽頭部のゴロゴロ音)が聴取される。これも意識が低下していれば、苦しくはない。
・橈骨動脈や上腕動脈を触知しなくなる。
・尿の流出が止まる。あるいは、相当低下する。
・看取りに居合わせたい家族はそばにいたほうが良い。
・呼吸は一般的に浅く速いである。呼吸が下顎呼吸となり、1分あたりの呼吸回数が数回程度となれば、分単位である。
※これらの時期は、終末期医療に習熟した複数の医療者で、また緩和ケアチームとの相談で、目安をつけるのが望ましい。
★1 最近の考え方では、身の置き所のなさ=倦怠感、とするよりも、高頻度のせん妄により身の置き所のなさが生じていると解することが多い。
2. 最後の症状と最期の様子と家族のすること
ひと口に終末期といっても、余命が月単位ある時と、週単位の時と、日単位、時間単位の時とでは、見た目の状況やよく出る症状は異なります。
多くの場合、余命が日にちの単位となると、せん妄の状態になります。
よく間違えられるのですが、意識が比較的清明に見えても、実際はせん妄状態に陥っていることは非常に多いです。
清明な時間があるからと言って、せん妄は否定できません。
むしろ日内変動があることが、せん妄の診断基準(DSM-5)には入っているくらいなのです。
せん妄も比較的穏やかなものもあれば、非常に興奮を伴い、ご本人にもご家族にも苦痛になる場合があります。
興奮が強いケースでは、暴言のようなことをおっしゃる場合もありますが、それは本意ではないので、ご家族は気をつける必要があります。
そしてそのような事例では、医療者にそれを緩和する処置を希望すると良いでしょう。
抗精神病薬もある程度有効ですが、終末期のせん妄はしばしば治療抵抗性で、「鎮静」という処置が必要になることも多いです。
3. 鎮静は安楽死ではなく、命も縮めない
このホームページでも度々説明していますが、鎮静は安楽死ではなく、命も縮めません。
ただし、鎮静薬を用いて意識を低下させることによって苦痛を緩和するので、コミュニケーションが難しくなります。
この鎮静に使う薬はモルヒネではなく、胃カメラを眠る際に使うのと同じ、ミダゾラム(商品名ドルミカム)という薬剤です。
またそもそもとして、この鎮静を考慮する際は、せん妄状態であることも多く、これらの薬剤を使わなかったからと言って、最後までしっかりコミュニケーションを図れるわけでもありません。
鎮静薬を使わない→意識清明、鎮静薬を使う→一切のコミュニケーション不可、と0と1で色分けできるものでもないのです。
そして鎮静薬を用いなくても、最後の数時間は意識が低下することがほとんどです。
その前までは、一般に、苦しそうな状況が続きますので、必要十分な鎮静が考慮されます。
4. それなので鎮静が検討される前段階で十分なコミュニケーションを図ること
鎮静が検討される時期はそもそも前臨死期といわれ、コミュニケーションは(鎮静を行わなくても)不安定になります。
それなので、その前段階で十分話し合うべきことは話してくことです。
せん妄が強い時期は、周囲は穏やかな対応を心がけてください。
罹患者の言動に必要以上に惑わされる必要はなく、穏やかに見守りましょう。
せん妄からの混乱や興奮が強ければ、医療者に対応を求めましょう。
せん妄をせん妄と取らないと、間違った治療(医療用麻薬の過大な増量)の元となるので、ある程度以上の緩和ケアの知識が医療者にも必要であり、またご家族の理解も重要となります(痛そう=痛みとは限らないので、鎮痛薬を求め鎮静薬を厭うというのは不合理な可能性があります)。
まだまだ終末期の真実はあまり知られていません。
ぜひ困っている方には、これらを知って頂く、あるいはこの情報をご紹介頂ければと思います。
膵臓がん末期の症状、余命や5年生存率、治療法など詳しく解説
■膵臓がんの転移について
膵臓がんの転移とは、がんが原発部位である膵臓から他の臓器や組織に広がることを指します。
膵臓がんは早期発見が難しいうえ進行が速いため、発見時にはすでに転移が見られるケースが多いです。。
以下に、膵臓がんが転移しやすい場所とその症状について説明します。
1. 膵臓がんが転移しやすい場所
膵臓がんが転移しやすい部位としては、肝臓、腹膜、肺、骨が挙げられます。
最も一般的な転移先は肝臓です。血液の流れによってがん細胞が運ばれ、肝臓内に新たな腫瘍が形成されます。また、腹膜や肺への転移も多く見られます。
骨への転移は、痛みや骨折のリスクを伴い、特に進行したがんでよく見られます。
2. 膵臓がんが転移した場合の症状
膵臓がんが転移すると、転移先によってさまざまな症状が現れます。
例えば、肝臓への転移では、肝機能の低下に伴い黄疸が生じ、皮膚や目の白い部分が黄色くなり、かゆみや倦怠感を感じることが多いです。また、肝臓の腫れや腹水の増加により腹部の膨満感が生じることもあります。
腹膜への転移では、腹痛や腹水の増加が見られ、食欲不振や体重減少がみられます。。
肺への転移では、咳や息切れ、胸部の痛みが現れ、呼吸困難を引き起こすこともあります。さらに、骨への転移では、激しい痛みがあり骨折のリスクが高まることがあります。
■膵臓がん末期の主な治療法とは?
膵臓がん末期は、がんが遠隔臓器にまで広がった進行した状態で、一般的に根治を目指すことは難しいとされています。そのため、治療の目的は主に、がんの進行抑制による延命や、痛みや不快な症状をやわらげる症状緩和となります。
選ばれる治療法は以下の治療法が多いです。
・薬物療法
・手術療法(緩和手術)
・放射線治療
・対症治療(緩和ケア)
・免疫療法
それぞれ解説します。
1. 薬物療法
薬物療法は、膵臓がん末期の治療において主要な役割を果たす方法です。主に抗がん剤を使用してがんの進行を抑えます。
膵臓がんの化学療法には、ゲムシタビンやフルオロウラシル(5-FU)などの薬剤が使用され、最近ではアブラキサン(nab-パクリタキセル)やフォルフィリノックス療法などの新しい治療法も効果を示しています。
これらの薬剤は、がん細胞の増殖を阻止し腫瘍の縮小を目指します。
化学療法は単独で使用されることもありますが、痛みや他の症状を緩和するための緩和ケアと併用されることが一般的です。
副作用として吐き気、疲労感、脱毛などが発生する可能性があるため、それらの管理も重要です。
2. 対症療法(緩和ケア)
対症療法(緩和ケア)は、膵臓がん末期において非常に重要な治療法です。主に痛みや症状を軽減し、患者さまの生活の質を向上させることを目的としています。
根治的治療が難しい場合でも、緩和ケアを通じて患者さまの苦痛を和らげ、できるだけ快適な生活を送るためのサポートが行われます。
具体的には、痛みを緩和するための鎮痛薬の使用や、黄疸や腹水に対処する治療が含まれます。
また、吐き気や食欲不振、倦怠感などの症状に対しても、それぞれに適した薬物療法が提供されます。
さらに、心理的サポートや栄養管理も緩和ケアの一環として重要視されます。
これにより、身体的な苦痛だけでなく精神的な負担も軽減することが可能です。
緩和ケアは、病状が進行した患者さまに最適なケアを提供しながら、治療の質を高めるために不可欠なアプローチです。
■末期の膵臓がんに関するよくある質問
末期の膵臓がんは、がんが進行した状態であり、患者さまやその家族にとって多くの不安や疑問が生じることが少なくありません。
ここでは、末期の膵臓がんに関するよくある質問について、わかりやすく丁寧に解説します。
1. 膵臓がんの余命一ヶ月の症状は何ですか?
膵臓がんの余命一ヶ月の段階では、がんの進行によってさまざまな症状が現れます。
具体的には、本記事の冒頭でお伝えした末期の膵臓がんの症状である
・持続的な腹痛や背中の痛み
・黄疸
・吐き気
・食欲不振
・消化不良
・消化酵素の分泌低下
・全身の衰弱感、疲労感
に加え、
・腸閉塞
・呼吸困難
などの症状が現れる場合があります。
余命1カ月の段階での腹痛や背中の痛みは非常に強く、日常生活にも影響があるため鎮痛薬の使用が必要になることが多いです。
また、肝臓への転移や胆管の圧迫により黄疸が悪化し、皮膚や目の白い部分が黄色くなるほか、全身のかゆみや倦怠感はさらに強まることがあります。
消化機能の低下に伴う、吐き気や嘔吐、食欲不振、全身のエネルギー低下による疲労感や倦怠感はより強く現れます。その結果、体重が急激に減少し全身の衰弱が進む。長時間の睡眠や意識の混濁が見られるといった場合があります。
さらに、余命1カ月の段階では、腸閉塞が起こることもあり、腹部の膨満感や激しい腹痛を引き起こす場合があります。
もし、肺への転移がある場合には、呼吸困難や咳が増えるといった症状が顕著になります。
これらの症状は進行がん特有であり、緩和ケアを通じて症状を軽減し、少しでも快適に過ごせるようサポートすることが重要です。
2. 末期がんの患者さまにモルヒネを投与するのはなぜですか?
末期がんの患者さまにモルヒネを投与する理由は、痛みを和らげるためです。
モルヒネは強力な鎮痛作用を持つオピオイド系薬剤で、がんによる痛みを効果的に緩和できます。
進行がんでは、腫瘍が周囲の神経や臓器を圧迫し患者さまの生活の質を大きく低下させるほどの激しい痛みを引き起こすことが多くあります。そのため、痛みの緩和は患者さまが少しでも快適に日常生活を送るためには欠かせない要素です。
モルヒネの使用には誤解や不安を抱くこともありますが、適切な投与量と管理のもとで使用すれば依存症のリスクは低く、副作用もコントロール可能です。
モルヒネは経口、注射、パッチなどさまざまな方法で投与され、患者さまの症状に応じて最適な方法が選ばれます。
また、モルヒネは痛みの軽減だけでなく、呼吸困難の緩和にも使用されます。特に末期がんの患者さまにとっては、呼吸困難の緩和は重要な役割を果たします。
3. 膵臓がんの痛みはどんな痛みですか?
膵臓がんによる痛みは、腹部から背中にかけて感じる場合が多く見られます。特に、背中にかけての鈍い痛みや、腹部の深部に差し込むような痛みが典型的です。
この痛みは、膵臓がんが神経や周囲の組織に浸潤することで生じ、徐々に強くなることが多いです。
痛みは持続的で、食事後や体を前かがみにしたときに悪化し、日常生活に大きな影響を与えます。
進行がんの場合、痛みはさらに激しくなる傾向があり、腫瘍が成長して神経に直接圧力をかけることで痛みが増します。
また、肝臓や腹膜に転移した場合、それに伴う痛みや不快感が加わることもあります。
慢性的な痛みにより、睡眠障害や食欲不振を引き起こすことがあります。