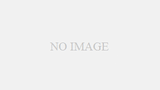がんリハビリテーションについて、勉強したので公開する
参照ページ
①がんリハビリテーション
https://www.az-oncology.jp/cancer_treatment/exercise/cancer_rehabilitation/
②腫瘍循環器リハビリテーション
https://www.npo-jhc.org/image/pdf/gan.pdf
➂ウォーキングはリハビリに効果的?適正な強度についても徹底解説!
https://www.mcsg.co.jp/kentatsu/health-care/42819
④歩数計アプリ「HealthPlanet Walk」の使い方ガイド
https://www.city.nishiwaki.lg.jp/material/files/group/10/healthplanetwalk_guide.pdf
➄レジスタンス運動(全9種類)
https://www.youtube.com/watch?v=Wx_D6XN1qaw
がんリハビリテーション
維持的リハビリテーション
対象:
・薬物療法によって倦怠感を自覚している患者さん
目的:
・倦怠感の軽減
リハビリテーションの内容:
・ウォーキングマシンやエアロバイクを使う有酸素運動や軽いストレッチや筋トレをおこないます。
がん治療中の運動について
がんの症状やがん治療の副作用で、からだの機能が低下したりストレスを感じることがあります。しかし、一般的には「がん治療中」という理由だけで運動を控える必要はありません。治療中に過度に安静にして過ごすと、筋力や関節のおとろえ、骨密度の低下、心肺機能の低下などの変化をきたすことがあります。
運動は、心とからだの両面からがんに向き合う力を向上させ、さまざまな効果をもたらします。主治医にどの程度からだを動かしてもよいかを確認しながら、可能な範囲でご自身でも日常に運動を取り入れてみましょう。
がんと診断された後は精神的なストレスはもちろん、がんそのものによる食欲低下、だるさ、痛みなどの症状で動きたくないと感じるかもしれません。また、安静にしておこうと考える患者さんも多くいらっしゃいます。実際に、がんの治療中、そして治療後は、患者さんの活動量は診断前に比べ、大きく低下するといわれています。しかし、診断直後から治療中、治療後に至るまで、身体を動かすことにはたくさんのメリットがあります。
がん治療中の身体の状態
身体の中にがんが存在していると、がん組織が正常な組織の栄養を奪ってしまうことによって身体の衰弱が起こりやすい状態にあります。それに加えて治療による負担や、精神的なストレスによっても、心身ともに疲れてしまい、身体を動かさなくなる、食欲が低下し栄養が十分に摂れなくなる、といった状況に陥りがちです。さらには、筋力の低下、身体の機能の低下が起こることでいっそう疲れやすくなり、疲れるから動かない、動かないせいでさらに体力が低下する、といった悪循環が起こります。この悪循環を断ち切るために必要なのが、運動療法と栄養療法です。
運動療法と栄養療法、2つの側面から筋肉量や体重の減少を防ぐことが大切です。
各時期のリハビリテーションの目的
通常のリハビリテーションは身体に何らかの障害が起こってから受けるのが一般的ですが、がん治療におけるリハビリテーションはがんと診断されたのち、治療前の機能の障害はまだない時期より予防的に開始されることがあります。がんやがん治療によって影響を受けた身体の回復力を高め、残っている身体の機能を維持・向上させることを目的におこなわれます。がんと診断された後、治療が始まる前であっても身体を動かすことは、治療による合併症や後遺症などを予防することにつながります。
がん治療において身体を動かすメリット
がん治療において身体を動かすことには以下のメリットがあるといわれています。
・体力・筋力の維持や改善
・だるさや疲れやすさの改善
・生活の質の改善
・手術による合併症・後遺症の予防
・手術後のスムーズな回復
・リンパ浮腫の予防や改善
・不安や気持ちの落ち込みの改善、リフレッシュ効果
目標
・1日20ー30分の有酸素運動(ウォーキング、自転車など)をおこないましょう。
・始めは1日10分でも構いません。徐々に時間を長くしていきましょう。
・週に2回は筋力トレーニングとストレッチをおこないましょう。
・1日合計15ー20分が目安です。筋力トレーニングをおこなう場合は、その日に動かす部位の筋肉を念入りにストレッチしましょう。
注意点
・主治医と相談し、無理のない範囲でおこないましょう。
・途中で息切れがしたり、きつい場合は無理せずに休憩しましょう。
腫瘍循環器リハビリテーション
(Cardio-Oncology Rehabilitation: CORE)
・「がん」を患うと、痛みや食欲の低下、だるさ、息苦しさなどを感じ、体を動かしづらくなります。また、手術や抗がん剤治療、放射線治療などで筋力が低下したり、身体機能が損なわれたりすることもあります。運動を中心とした「がんリハビリテーション」により、これらのつらさを軽くし、生活の質を改善することができます。
・がんリハビリテーションは、がん治療中のできるだけ早期から開始することがすすめられています。がんリハビリテーションは、適切な運動療法に加え、病気や体調を良く理解し、それらに対する適切な対処法を学んだり、食事や栄養の知識を深めたりすることも重要な要素になります。さらに、適切な運動が、がんによる死亡リスクを軽減するとされています。
・心臓や血管は、抗がん剤や放射線療法などのがん治療により障害をうけます。ときには、心臓の筋肉が弱り心臓ポンプ機能が低下することもあります。抗がん剤や放射線療法が原因で動脈硬化が進み、心筋梗塞や脳梗塞を発症することもあります。そして、がん治療中の心臓や血管の障害には、もともと持っている高血圧、肥満、糖尿病、脂質異常症、そして運動不足などの危険因子がさらに悪影響をおよぼすと言われています(図 2)。
・がん治療は心臓や血管ばかりでなく、全身の筋肉への悪影響があり、筋力の衰えや筋肉量の減少などで疲れやすくなります。そこで、がん治療によりダメージを受けた心臓や血管を回復させるために、がんに対しても心臓リハビリテーションを取り入れることが重要と考えられるようになりました。
・例えば、乳がん患者の生存率は向上していますが、心血管疾患による死亡の割合は高く、乳がんの診断から 10 年以降では、心血管疾患による死亡は乳がんによる死亡より多いのです。
・そこでご紹介したいしたいのが、腫瘍循環器リハビリテーション (CORE: Cardio-Oncology Rehabilitation) です。CORE は心臓リハビリテーションの考えを取り入れた、がんのリハビリ テーションです。CORE を適切に行うことで生活の質 (QOL)の改善、心肺機能の向上、がんや心臓病の再発 予防や生命予後の改善が期待できます。
・つまり、がんになってもより元気で長生きを目指せます。
準備運動
・準備体操やウォーミングアップにあたる運動です。体を温めて、筋肉や関節の動きを滑らかにしたり、全身の血流を促して筋肉組織への酸素の供給を増やしたりする効果があります。
・一般的に、運動を急に始めると、心拍数や血圧などが急上昇して不整脈が起きたり、筋肉に急激にストレスが加わったりする恐れがあります。こうした危険を防止し、安全に運動を始めるために、まずは準備運動を行うことが大切です。
それぞれ5~10回
運動の種類
・COREで使われる運動には、大きく分けて有酸素運動(持久的運動)とレジスタンス運動(いわゆる筋トレ)があります。
・息止めをしていきみながら行う強い筋トレは、血圧上昇をきたすばかりでなく、効果も少ないと考えられており、頑張りすぎるトレーニングは不適切と考えられています。
有酸素運動
・ウォーキングや自転車こぎ、軽いエアロビクスのような、身体に酸素を取り入れながら比較的大きな筋肉を使って全身をリズミカルに動かす運動のことです。
・30 分運動して息切れしてしまうのは有酸素運動とは言えません。
・運動処方箋に従うか、または、「少し汗をかき、息があがらず、会話をしながら運動できる程度の運動」が適しています。
・膝や腰の痛みがある場合は専門の医師と相談し、水中ウォーキングから始めるのもよい選択です。
※有酸素運動の処方例
・時速3km から4km の速度で、心拍数が 100 回 / 分程度となるようなウォーキングを1 日 1 回 30 分、週に 5 日程度行う。
頻度のめやす:3〜5日/週
強度のめやす:普段歩いているよりも少し早歩き(息切れが生じない速さ)
時間のめやす:持続的な有酸素運動で20〜60分/日。しかし、この時間が耐えられないのであれば数回に分けて合計20〜60分/日
レジスタンス運動
・同じ運動をつづけて 10〜 15 回できる程度の運動の強さを決めて、それを 1 セット 10 回程度、1 日に 1〜 3 セット行います。
・レジスタンス運動は 1〜 2 日おきに実施します。
・筋肉は運動をすると一時的に機能が低下しますが、2〜 3 日後には運動前より機能が改善します。そこでまた次の運動をするとより効果的とされています。
・フィットネスジムでマシン運動ができると理想的です。自宅では椅子などにつかまって安全に実施する屈伸運動などもおすすめです。
レジスタンス運動を安全に行うために
・準備運動を行い、最初から強い負荷は避ける。
・大きな筋肉を使った運動をする。
・呼吸を止めない。力を入れておもりを上げる際には息をはく。
・おもりは 2 秒で持ち上げ、4 秒でゆっくり下ろす。
・反復の間には必ず休みを入れる。
・過剰な血圧上昇を避けるため、グリップは軽く握る。
・血圧と脈拍数の反応は使う筋肉の量と収縮の強さに比例するので、片側ずつ行う。
・ひじやひざは完全に伸ばさず、少し余裕をもたせる。
・正しいフォームで、動かす筋肉を意識して運動する。
重要! いつもと違う症状、特にめまい、不整脈、息切れ、胸の痛みや圧迫感が現れたらすぐに中止する。
栄養
・栄養管理は、がんリハビリテーションと心臓リハビリテーション、つまり、CORE において大変重要です。糖尿病や脂質異常、そして塩分摂取が多く血圧が高い場合など、これらは心臓病や動脈硬化の悪化につながります。
・一方、がんの診断時に既に半数の方で体重減少がみられると言われ、がん治療中も食事のバランスはくずれがちです。そして、がんの手術後はかなり全身の筋肉量が低下すると言われています。栄養状態が悪い状態で無理に運動を行うと、筋力がつくどころか消耗してしまうこともあり注意が必要です。適切に栄養を摂取し、効果的に運動に取り組むことが重要です。退院時にはしっかりと栄養指導を受け、その後も時々栄養士に相談しましょう。
ウォーキングはリハビリに効果的?適正な強度についても徹底解説!
1.ウォーキングによるリハビリの効果は?
・ウォーキングは高齢者・病気やケガをした方のリハビリに効果的とされています。
・ウォーキングによるリハビリ効果とは具体的にどのようなものなのか、ご紹介していきます。
■心肺機能が高まる
・ウォーキングには心肺機能を高めるリハビリ効果があります。
・ウォーキング中は、多くの酸素を体内に取り込むためです。
・ウォーキングをして酸素を多く吸い込むと、肺がしっかり広がります。
・肺で取り込まれた酸素は、血液に乗って、心臓から全身へと送り出されます。
・簡単にいえば、心肺が忙しく働かなければならないため、自然と機能も強化されるというわけです。
■心臓・血管の健康が維持される
・ウォーキングには心臓・血管を健やかに保つリハビリ効果があります。
・ウォーキングをすることで血流が促進されるためです。
・なぜウォーキングをすると血流が促進されるのでしょうか。
・答えは、運動中に体内に取り込んだ酸素を血液に乗せて全身に届けようとするためです。
・血流が増えると、心臓を収縮させる筋肉(心筋)の動きが活発化します。
・自然に心筋が鍛えられるため、心臓機能が強化されます。
・一方、心臓から送り出された酸素(血液)は血管を通って全身を巡ります。
・血流の増加は、血液の通り道である血管の拡張をもたらします。
・血管が適度に拡張すると、血流が血管の壁に与える圧力が軽減されます。
・簡単にいえば、血圧が下がります。
・血圧が下がると、血管・心臓への負担が軽くなります。
・結果として、血管・心臓の健康が維持されやすくなるのです。
■骨密度が向上する
・ウォーキングには骨密度の減少を防ぐ効果が期待できます。
・理由は、着地の際に体に適度な衝撃が加わるためです。
・体に物理的な衝撃が加わると、骨細胞の中のNF-κBの働きが弱まります。
・NF-κBは古い骨を破壊するプロセスに関わる酵素です。
・NF-κBが抑制されると骨の破壊がゆるやかになるため、骨密度の減少を防げます。
・骨密度の維持・向上は骨粗鬆症の予防につながります。
・骨粗鬆症とは骨が脆くなる病気で、骨折や寝たきりの大きな原因の1つです。
・出典:厚生労働省【骨粗鬆症予防のための運動 -骨に刺激が加わる運動を | e-ヘルスネット】
■認知症を予防する
・ウォーキングには認知症の予防効果が期待されています。
・ウォーキングは脳の活性化をもたらすためです。
・ウォーキングが脳を活性化させる理由は主に3つあります。
・1つめは脳への血流が増加するためです。
・ウォーキングによって全身の血流が促進されると、脳への血液供給も増えます。
・すると脳が十分な酸素・栄養を受け取れるため、働きが活性化しやすくなります。
・2つめは脳神経の成長が促進されるためです。
・ウォーキングによって体を動かすと、筋肉からアイリシンというホルモンが分泌されます。
・アイリシンは、海馬でのBDNFの分泌を増やす働きがあります。
・BDNFは脳由来神経栄養因子です。
・具体的には、脳神経細胞の成長・維持・再生やシナプスの形成を促します。
・海馬でのBDNF分泌が増えると、海馬が活性化します。
・さらに海馬の容積の増加も見込めます。
・海馬は記憶・学習などの認知機能を司る脳器官です。
・認知症では多くの場合、海馬の萎縮や不活性化が認められます。
・裏を返せば、海馬の肥大・活性化は認知症を防ぎやすくなります。
・ウォーキングはBDFNを増やして海馬を強化することで、認知症のリスクを下げるのです。
・3つめは生活習慣病を防ぐためです。
・認知症は、生活習慣病などから発展することもよくあります。
・理由は、病気のために体を動かせなくなったり、寝たきりになったりするためです。
・体を動かさなくなると、脳への刺激も減ります。
・結果、脳が不活性化して認知機能の低下を招きます。
・ウォーキングは健康維持に役立つ運動です。
・病気による不活発化・寝たきりを防ぐことは、ひいては認知機能の低下の抑制につながります。
■ストレスが軽減する
・ウォーキングにはストレスを軽減する効果も知られています。
・主な理由は2つあります。
・1つ目はセロトニンの分泌を促すためです。
・セロトニンはイライラを鎮めたり、幸福感を高めたりするホルモンです。
・セロトニンは、規則的な運動を行うと分泌量が増えます。
・たとえばウォーキングのように、一定のリズムで歩行する運動が適しています。
・2つめは筋肉の硬直がほぐれるためです。
・体がほぐれると、心も自然とリフレッシュしやすくなります。
・出典:スポーツ庁【プラス「10」分のウォーキングから始めるストレス対策】
■免疫力が向上する
・ウォーキングは免疫力の向上に役立ちます。
・主な理由は2つあります。
・1つめは血行が促進されて体温が上がるためです。
・適度に体温が上がると免疫細胞が活性化します。
・2つめは自律神経が整うためです。
・自律神経は、免疫機能・血圧・心拍などを管理している神経系です。
・自律神経はストレスなどでリズムを崩しがちです。
・一方、ウォーキングはストレスを解消する効果があるため、ひいては自律神経の改善に役立ちます。
・自律神経が整うと、免疫機能も正常に維持されやすくなります。
■血糖値を下げる
・ウォーキングには血糖値を下げる効果が期待できます。
・主な理由は2つあります。
・1つめは、運動のエネルギー源として血中の糖が消費されるためです。
・運動すると筋肉の修復のために、血中の糖が筋肉に取り込まれます。
・結果として、血液中の糖の量が減少します。
・2つめはインスリンの効きを良くするためです。
・インスリンは血糖値を下げるホルモンです。
・運動をすると筋肉量が増加します。
・インスリンは、筋肉が増えることで効きが良くなります。
■肥満や生活習慣病の予防
・ウォーキングには肥満・生活習慣病を予防する効果も期待できます。
・たとえば次のような生活習慣病予防に役立ちます。
- 高血圧
- 動脈硬化
- 糖尿病
- 脂質異常症
- 脳卒中
- 心疾患(心筋梗塞・狭心症)
・出典:厚生労働省【ウォーキング | e-ヘルスネット】
■腰痛予防から美肌効果も
・ウォーキングには、その他にもさまざまな効果が期待できます。
・代表的な効果は次の通りです。
- 腰痛予防:腰回りの筋肉が強化されるため
- 美肌効果:新陳代謝が良くなるため
- ボディメイク:肥満が解消されてボディラインが整う
- 社会的効果:外に出ることで他人との交流が生まれる
2.リハビリにおけるウォーキングの適正な強度
・リハビリ効果を高めるには、適切な方法でウォーキングをする必要があります。
・ここからは、リハビリのための適切なウォーキングの方法をご紹介していきます。
■ウォーキングの歩数は8000歩
・リハビリ効果を高めるには、ウォーキングの歩数は1日8,000歩が適当です。
・1日8,000歩歩く方は、そうでない方より全原因の死亡率が約15%低いとされています。
・心血管系の死亡率に限定すると、1日8,000歩の方の死亡率は約8%低いという調査結果が出ました。
・8,000歩は小分けにしてもかまいません。
・たとえば3,000歩・3,000歩・2,000歩のように合計で8,000歩を目指しましょう。
・いきなり8,000歩が難しい方は、1,000歩ずつ歩数を増やすようにしてください。
・8,000歩の運動のうち、約20分間はやや強度の高い運動をするのが良いとされています。
・たとえば早歩きをしてみましょう。
■ウォーキングは週1〜2回
・リハビリ効果を得るには、少なくとも週に1〜2回のウォーキングがおすすめです。
・余裕がある方は、週3回以上を目指してください。
■ウォーキングは息が軽く弾む程度の強度
・リハビリにおすすめなのは、息が軽く弾む程度の速度でのウォーキングです。
| ウォーキング | 筋トレ | |
| 筋肉増強 | △ | ○ |
| 内臓脂肪の減少 | ○ | △ |
| 糖の消費 | △ | ○ |
| 心肺機能の強化 | ○ | △ |
| 血圧を下げる | ○ | △ |
■ウォーキングと筋トレの目的が違う
・ウォーキングと筋トレでは目的もやや異なります。
| ウォーキング | 筋トレ | |
| 筋肉増強 | △ | ○ |
| 基礎代謝の向上 | △ | ○ |
| 健康維持 | ○ | △ |
| 時間 | 長時間できる | 短時間が適当 |
| 運動強度 | 低い | 高い |
・ウォーキングは運動強度が低いため、身体機能の低い方でも取り組みやすいのが特徴です。
・対して筋トレは、ある程度の身体機能を持つ方に適した運動です。
・リハビリ目的であれば、強度の低いウォーキングが向いているでしょう。
・よりリハビリ効果を高めるには、ウォーキング・筋トレの両方に取り組むのもおすすめです。
・順番は筋トレ・ウォーキングのように行いましょう。
・筋トレ→ウォーキングの順番で行うことで、成長ホルモンの分泌が促進されるためです。
・成長ホルモンには脂肪燃焼・骨の成長の促進や、筋肉の疲労を修復する作用があります。
3.ウォーキングによるリハビリの注意点
・ウォーキングでリハビリを行う際の注意点をご紹介します。
・ウォーキングがかえって健康を損なう原因とならないよう、ぜひ参考にしてください。
■持病がある方は主治医に相談
・持病がある方は、ウォーキングをしたい旨をまずかかりつけ医に相談してください。
・身体状況によっては、ウォーキングによって体調が悪化するおそれがあるためです。
・特に高血圧症・心疾患のある方は、必ず事前に医師に相談してください。
■ウォーキング前後にストレッチをする
・ウォーキング前には必ずストレッチをしましょう。
・いきなり運動をすると、筋肉や関節を痛めるおそれがあるためです。
・まずはストレッチをして、筋肉・関節をゆるめましょう。
・ウォーキング後のストレッチも重要です。
・ストレッチをすることで、筋肉がクールダウンして疲労が回復しやすくなります。
・ストレッチはウォーキング後30分以内に行いましょう。
■体調が悪い時は無理に行わない
・体調が悪いときは、無理にウォーキングをする必要はありません。
・無理をすると、健康を損なうおそれがあります。
・もし運動中に体調が悪くなった場合は、すぐに休憩しましょう。
■適度な水分摂取を行う
・ウォーキング中は発汗が促進されます。
・脱水症状を防ぐために、適度な水分補給を行ってください。
・たとえ喉が渇いたと感じなくても、水分補給は必ず行ってください。
・高齢者の方は、喉が渇いたと感じる機能が低下していることが多いためです。
・10分に1回のように給水のタイミングを決めておくと、脱水を防ぎやすくなります。
歩数計アプリ「HealthPlanet Walk」の使い方ガイド
アプリの初期登録フロー(Android)
①アプリをダウンロードする
・「Playストア」を開きます。
・Playストアのアプリ検索画面で「ヘルスプラネットウォーク」と検索し、アプリをダウンロードしてください。
②アプリを起動する
・ダウンロードされたアプリがトップ画面に存在しているか確認します。
・アイコンをタップしてアプリを起動させたら「次へ」をタップします。
➂ログインをして目標設定をする
・ログインIDとパスワードを入力し「ログイン」をタップします。
・プロフィールで「次へ」をタップします。
・歩数目標を入力し「次へ」をタップします。
④モードを「内蔵歩数計」にする
・「設定」でモードを「内蔵歩数計」にし、「始める」をタップしてください。
・ホーム画面が起動します。
・その他の各項目に関しましては、「その他」 > 「このアプリの使い方」で確認することができます。
➄スマホの設定を確認する
・ホーム画面上の「設定」をタップします。
・「プライバシー」をタップします。
・「権限マネージャ」をタップします。
・「身体活動」をタップします。
・「HealthPlanet Walk」が許可されていることを確認。
・許可されていない場合は「HealthPlanetWalk」 をタップし、「許可」を選択します。
アプリの機能
HealthPlanet Walk(ヘルスプラネットウォーク)は、歩数を記録するアプリです。歩数消費カロリーや歩行時間、歩行距離なども計測します。
【主な機能】
・1日または1週間の歩数を円グラフと数値で表示する
・1日または1週間の目標達成を歩数グラフで確認する
・1日または1週間の歩数目標を設定する
・歩数・歩数消費カロリー
・歩行時間を日別にリストで表示する
・24時間分の歩いたルートを表示する
・音楽を聴きながら歩くことができる
【設定項目】
・体組成情報(性別、生年月日、身長、体重、体脂肪率)の設定
・歩幅(自動設定のON/OFF設定)
・加速度センサーのON/OFF
・スタミナモードのON/OFF
・省電力モードのON/OFF
・自動再起動のON/OFF
【連携機能】
・ヘルスプラネットと同一のIDでログインすることで、ヘルスプラネットWalkのデータがヘルスプラネットに送信される
・iPhone、iOSの「ヘルスケア」アプリと連携できる
【注意点】
・アプリを停止すると歩数がカウントされない
・アプリにスマートフォン内蔵の加速度センサー利用を許可する必要がある